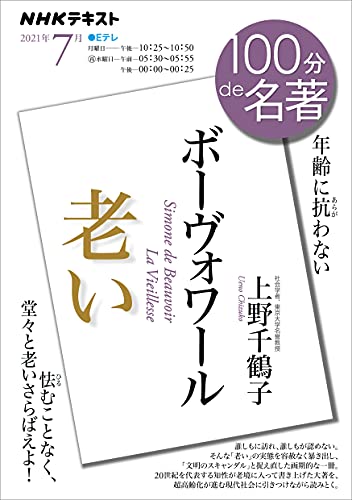
NHKテキスト「100分de名著」2021年7月号 ボーヴォワールの「老」を読んだ。
本屋でいつも100分de名著のテキストを見ると、いつも立ち読みして、興味があれば本も買って読みたいと思う。
だがテキストの隣に置いてあった「老」の上下巻本の分厚さに圧倒されてしまい購入を躊躇してしまった。
まずテキストを読んでから判断しようと思ったのだ。結果として、テキストを読み終わると、まるで本を全て読破してしまったかのような錯覚を覚えてしまった。上野千鶴子さん(社会学者、東京大学名誉教授)の解説が分かりやすかったからだ。
ボーヴォワールは、サルトルと並び、戦後フランスにおいて実在主義の思想を掲げて活動した作家・哲学者である。
ちなみに夫はサルトルである。
「老いは文明のスキャンダルである」
文明社会でありながら、老いた人間を厄介者にして廃棄物扱いにする。そのように老人を扱うことが文明のスキャンダルであると、ボーヴォワールは言います。つまり老いは個人の問題ではなく社会の問題である、ということである。
ボーヴォワールは、厄介者になった高齢者をどう扱うかで、その社会の質が測られると言っている。
まさにこの現代に改めてボーヴォワールの言葉の意味を深く考える時ではないだろうか。
ボーヴォワールは、変革のためにはまず現実を知ることが必要、とのことで、膨大な資料を読み解いて、厄介者扱いされる高齢者の現実を直視します。また「自分は厄介者になってしまった」と悲嘆する高齢者の心理を直視します。
大人が老人に向かう、いわゆる向老期についてはこれまで問題にしなかった(当時は寿命が短く、みんな早く死んでいたから)が、青年期よりもはるかに長くなった向老期でいかにアイデンティティを持ち続けることができるか。
文明の発展により人の寿命は延びた。高齢者と呼ばれる人たちが、人口の一定の割合を占めるようになってきた。彼らを文明社会はどう処遇するのか。それが、ボーヴォワールが投げかける最大の問いである。
まさかここで自分の考えを述べるわけではないが、考えさせられることが多々あることは事実である。
もしかしたら「老」を読んでも、このテキストの解説による助けがなければ、深くこの本、ボーヴォワールを知ることは難しかったのかもしれない。
高齢者に社会的役割や生き甲斐を求めれば求めるほど、それがなくなった時の自分に対して、自己否定感を持つのは当然だと思う。
だけど、年をとれば誰でも衰えて弱くなり、動きも鈍くなって、周囲に面倒をかけることもある。
だけど、それがどうした、その何が悪い?とうポジティブな老いの生き方、が重要なのだと感じた。
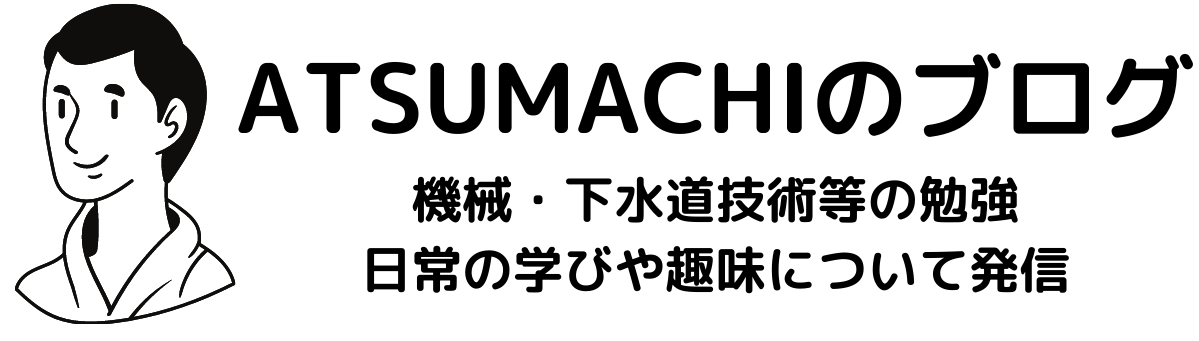
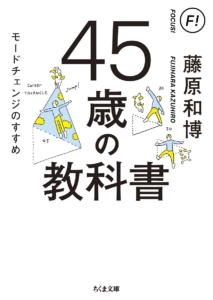
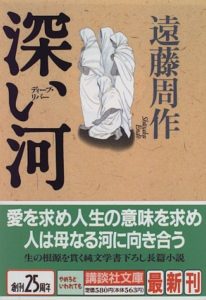
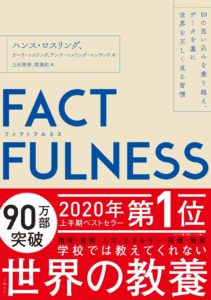
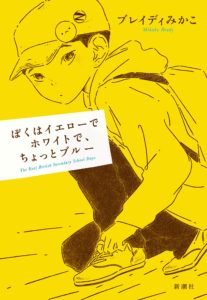
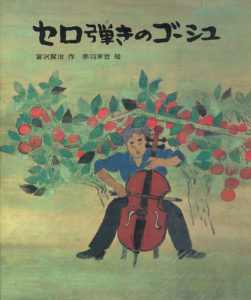
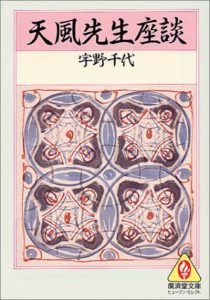

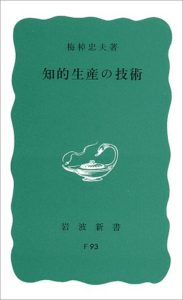
コメント