公害防止管理者等国家試験の勉強中である。
といってもさほど熱を入れて資格を取得しようとしているわけではない。
この資格試験は大気、水質、騒音・振動などの区分があり、それぞれで資格を取得できる。
自分が受験するのは騒音・振動関係である。この試験は科目があり、例えば騒音・振動関係では「公害総論」、「騒音振動概論」、「騒音振動特論」がある。科目別合格制による試験科目免除があり、昨年、公害総論、騒音振動概論は合格していたので、残りは騒音振動特論だけである。
免除は2年間しか有効ではないので、来年までに騒音振動特論が合格できないとリセットされてしまう。
自分が関わる業界ではむしろ水質や大気を勉強すべきなのかもしれないが、業務に直結するのはむしろ騒音・振動の方なのでこちらを選んだ。
試験を受験する目的は資格勉強を行う過程で業務に必要な技術知識レベルを高めることに主眼を置いている。
だが業務と直結する内容とそうでないものもあり、中々、勉強すること自身が苦痛でもある。
資格試験用のテキストを見ると様々な公式がでてくるのだが、式の導出」や物理的意味を理解しなければただ覚えるだけでなんの意味もないだろう。
式を覚えて使うだけ、物理的な意味を理解していなければ誤った使い方をする可能性もあるし、そもそもわざわざ、覚える必要もない。
昔、高校の勉強でいちいち、数学や物理の公式でつまずいたものだが性格上、とことん、その式が意味する物理的意味や導出過程を把握できていなければ勉強する意味がないとも感じてしまう。
とにかく公式を扱えるようにし、物理的な意味は繰り返し使う過程で覚えていくという考えもあるが、今はその考えになりつつある。
メーカにおける技術者は少なくとも技術分野において自己啓発を続けなければ成長はない。
日々の業務はただの作業に追われることが多いが、問題解決力や創造力を発揮するためには実践が重要だが土台となるには基礎的な学習が不可欠だとと感じる。
そう考えると自己研鑽のために一人で勉強する時間を作ることも大切だと思う。
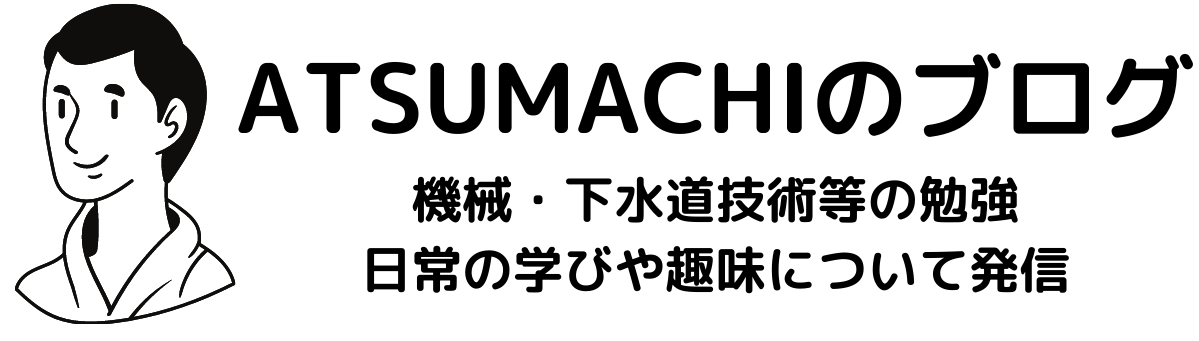


コメント