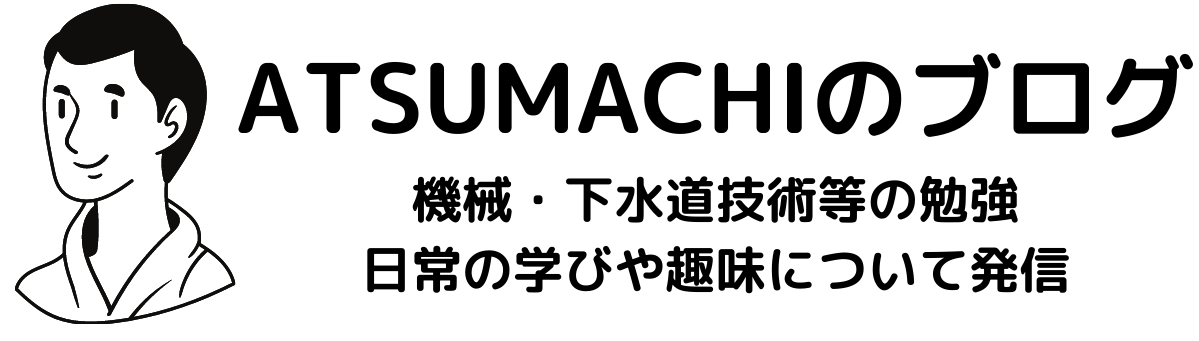デカルトは「この序説で自分がどういう道をたどってきたかを示し、1枚の絵のようにそこに私の人生を描」こうとしている。その意味で、かれの精神の歴史と展望を語っているという一貫性がある。
この書が訴えているものが近世哲学のはじまりとなる数々のマニフェストを表明していることは間違いない。
自分の人生をふりかえってみるとき、幼いころの出来事や学校で学んだことなどが懐かしく思われるものである。
自らの原点をそこに見出すからであろう。
序説は次のような文章ではじまる。
「良識はこの世で最も公平に配分されたものである」
良識とは「よく判断して真と儀とを区別する能力、すなわち本来理性と呼ばれているもの」のことである。
「だれでも自分は良識を十分に備えていると思っている」ので、「それはすべての人において生まれつき平等である」と言えるとしている。
「わたしたちの意見が分かれるのは、ある人が他人よりも理性があるということによるのではなく、ただ、わたしたちが思考を異なる道筋で導き、同一のことを考察していないことから生じるのである。というのも、良い精神を持っているだけでは十分でなく、大切なのはそれを良く用いることだからだ。」
子どもの頃、なぜ正しい道、真理は1つだけなはずなのに、皆が意思を統一することができないのか。政治の世界では派閥なるものが存在していることが不思議でならなかった。
もちろん、人は知識、知見がなく、判断を誤ることもあるのだが、政治家達が議論し合い、決議されるべき結果は正しい道、真理であるはずなのに、派閥とはどういうことなのかと子ども心に思った記憶がある。
そして次のような文章につながる
「大きな魂ほど、最大の美徳とともに、最大の悪徳をも産み出す力がある。またきわめてゆっくりと歩む人でも、つねにまっすぐな道をたどるなら、走りながら道をそれてしまう人よりも、はるかに前進することができる。」
人間は国籍や時代にかかわりなく、みな同じ高度な知性を内に持っている。それが精神であり、理性である。
めいめい努力してそれをうまく使用すれば共通理解が得られるはずである。ところが、その努力をせずに自己主張ばかりするところからさまざまな問題が起こる。
人にはそれぞれ独自の感性やものの考え方があろうが、他社とのコミュニケーションの場ではやはり理性が基本であり、理性を導く方法が必要である。たとえば、異文化の理解や他者との共生においては、お互いに自他の違いを認め、たとえ多様であっても、ともかく人間に共通に与えられた理性を使って問題を処理するしか他に手はない。
こうして自分なりの方法論を確立することが重要であるとの考えになる。
方法序説の中でデカルトは学校で学んだ諸学問の吟味している。つまり学校で学んだ諸学問が当初期待したような確実な認識を教えず、確実で人生の役に立つ学問こそデカルトが求めていたものである。
では確実とは何か。デカルトは「1つのことについては真理は1つしかない」という信念があった。逆に言えば、同じことに関して多様な意見が多出することは真理に達していないことの証拠である。
確実とは、だれが見ても明証的にそうだと言えること、疑いを差しはさむ余地のない真理ということである。
さしあたって数学の推論が確実だと考えられる。数学は明証的な直観と確実な演鐸による体系だからである。
いずれにせよ日常の生活や実学に結び付く学問が最終的に目指されている。
こうして真理を導く方法論としてデカルトは4つの規則を設けている。
1.偏見や即断を避け、明らかな真だけを受け入れる。
2.難しいことは分けて考える。
3.単純なことから順序立てて始める。
4.見落としがなかったか確かめる。
こうした方法論は普段の生活、ビジネスでも求められる。結果として要求されるものが何か。過去に似たものとしてどんなことがあるか。相手が要求している水準に達するためにはどういう手段、方法を用いれば実現できるか。これを極めて理性的に考える。
またいくつかの格率が示されるが、最も響言葉は以下だ。
「世の中の秩序を変えようとするのでなく己の欲望を変えよ」
運命じゃなくて自分に勝つ。優秀な人間は環境に不満を言わない。
こういった考えが大切なのだと実感する。