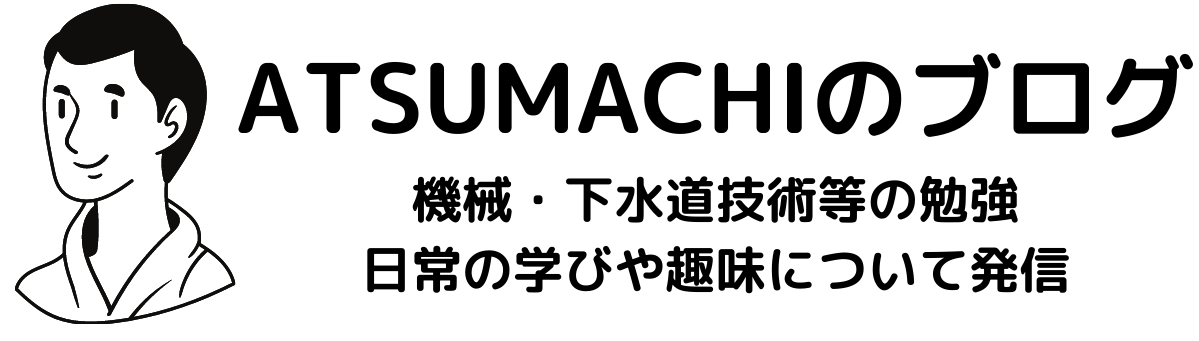第一次大戦後から二十年間の間のヨーロッパを中心とする世界情勢に対して、これだけ高度に世界情勢を精密かつ幅広く考察した人はいないのではないか、と思う。
理想主義と現実主義の相克と確執、粘り強く結論に導く粘り強さと分析力には頭が下がる。
第二次世界大戦前の情勢を現在を対比すると、さほど過去から変わっていないとも感じる。国際政治とは何か。国という枠をはずして組織を考え、平和とは何かを考える。
学ぶことが多い必読の本である。
「危機の20年より引用」
<学問の出発>
・ところが1914年~1918年の第一次世界大戦は、戦争が職業軍人だけに関わる重大事であるという見解を霧消させ、それとともに、国際政治が職業外交官の手に委ねておけば間違いないのだという考えを同じく消し去ってしまった。国際政治を広く国民のものにするという運動は、秘密条約反対運動という形をとって英語圏諸国で始まった。信ずるに足る十分な証拠があったとはいえないが、秘密条約は戦争の原因の一つとして非難されたのである。秘密条約の責めは、政府の悪意にではなく、一般国民の無関心にこそ帰せられるべきであった。というのも、このような条約が結ばれたことは誰でも知っていたからである。しかし1914年の戦争以前は、こうした秘密条約について詮索する人は少なかったし、それに異を唱える人もあまりいなかった。とはいえ、秘密条約反対運動は限りなく重大な出来事であった。なぜならこの運動は、国際政治を国民のものにしたいという願望の最初の兆候であり、新しい学問誕生の先駆けとなったからである。
・ある現代の社会学者は書いている。「どのような方法で体系化するのか、対象のどの部分に重点を置くのか、われわれが問いかけ答えようとする問題をどのように設定するのか、もしこれらのことを直接的かつ人間的な関心にうごかされてきちんと決めることができないなら、われわれは星や岩や原子についてさえ研究することはできないのである」。
・健康を増進したいという目的が医学を生む。橋を建設したいという目的が工学を生む。政治体の病弊を治したいという欲求が、政治学に弾みと刺激を与えたのである。意識しようとしまいと、目的は思考の先行条件である。思考のための思考は、蓄財のための蓄財をする守銭奴と同様、異常であり実りないものである。「願望は思考の父である」という言葉は、人間の真っ当な思考の始まりを完全に言い当てている。
・研究者が出す結論は、事実についての正確な報告以外の何ものでもない。研究者の結論が、あるがままの事実と異なる事実を作り上げることは許されない。なぜかといえば、事実は、人がそれについて考えていることとは関係なく存在しているからである。
・政治学が対象とする事実は、これを変えたいと思えば変えることのできる事実なのである。そして、すでに研究者の心のなかにあるこの変革への欲求は、研究結果の次第では他の多くの人々を動かして現実のものになっていくのである。
・自然科学と違って、政治学における目的は研究内容と無関係ではありえず、研究内容から目的を切り離すことはできない。目的はそれ自体一つの事実なのである。理論的には、事実を立証する研究者の役割と、正しい行動の在り方を考える実践者の役割との間に一線を引くことは確かに可能である。しかし実際には、一方の役割が知らず知らずのうちに他方の役割へと変わっていく。目的と分析は、一つの過程の本質的部分をそれぞれ構成しているのである。
・「最も原始的な種族」の特徴として、「ある見解が正しいということを証明することと、その見解通りの状態になって欲しいと期待することとがいまだ区別できないこと」を挙げている。
・目的を掲げて願望が強く出る初期の段階は、人間思考の本質的な基盤である。願望は思考の父である。目的論は分析に先行するのである。
・国際政治学の目的論的性格は、初めから顕著であった。国際政治学は、大規模かつ悲惨な戦争から生まれた。この新しい学問の先駆者たちを支配し鼓舞した決定的な目的とは何だったのか。それは国際政治学が抱えるこの戦争という病弊の再発を防止することであった。戦争を防止するという熱い願望こそが、この学問のそもそもの進路と方向をすべて決めたのである。
・揺籃期にある他の学問と同様、国際政治学は際立ってしかもあからさまにユートピア的であった。国際政治学の初期の段階では、願望が思考に、一般論が観察にそれぞれ優っていた。そしてこの段階では、現に存在する事実や利用される手段批判的に分析しようとする試みはほとんどなされていない。この段階では、達成すべき目的にもっぱら関心が集中される。目的が極めて重要であるがために、手段が提案されてもこれを批判的に分析するなどというのは有害無益だという烙印を押されること請け合いであった。